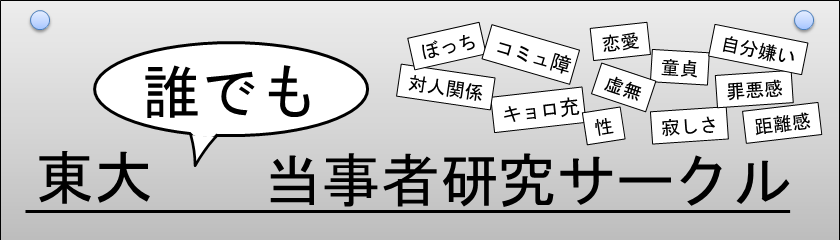現代社会の生きづらさと「解釈の権限の所在を決定する権限」
執筆者 べとりん
現代社会特有の生きづらさの正体を、「解釈の権限を決定する権限」という概念を用いて説明を試みる。
「解釈の権限」とは
定義:
ある事物や出来事の「意味」が、何によって決定されるかを表すもの。
例:「13とB」

この画像を見てほしい。これは心理学の「文脈効果」の説明のために用いられる図形である。
左の図は「ABC」、右の図は「12 13 14」と書かれているが、この「13」と「B」は全く同じ文字である。この文字の読み方は、どちらが正解なのだろうか。
この問題に正解はない。なぜなら、中央に書いてあるのはこのような形の「図形」に過ぎず、いわゆる「インクの染み」に過ぎない。「13」とか「B」というのは、あくまで読んだ者がこのインクの染みを勝手に「解釈」した結果である。
しかし、私たちは何も言われなければ普通これを「13」もしくは「B」として読むし、またそのような「意味づけを持ったモノ」としてしか認識しないだろう。「こんなの単なるインクの染みじゃないか」と考えだすのは、そこから意味を読み取ることに「一度失敗してから」である。そして、その意味付けは、「ABC」という一連の中で読むか、「12 13 14」という一連の中で読むかによって変わり得る。どのようにその物事を「解釈」するかによって、その物事が持つ「意味づけ」は変わるのである。
物事の「意味」は、見る側の「解釈」によって変わり得る。
だが、「解釈」は、必ずしも「見る人」が決定するものではない。
例:「風邪」
身体の体調が悪い。喉に違和感があり、熱っぽい。これは重病かもと思ったが、ある医者の元を訪ねたら「ただの風邪ですよ、大したことはありません」と言われたので、「そうか、(この体調の変化は)ただの風邪か、大したことはないのだな」と納得した。
しかし、数日たってみて、体調が悪化したので再度別の病院に行ったところ、肺炎だった。
「身体の不調」という出来事に対して、私は「重病かも」と思ったが、医師から「大したことはない」と言われ、この身体の不調は「大したことはない」という解釈に書き換えられた。つまり、私にとって「身体の不調」が何を意味するかは、私ではなく医師によって決められた。
これは、「身体の不調」という出来事については、私よりも医師の方が「知識があり」「よりよく判断できる」だろう、という前提があるからである。そのため、私の解釈よりも医師の解釈の方が優先するのだ。
つまり、この状況(診察室)では、「身体の不調」に対する「解釈の権限」は、私ではなく医師の方にある。
「解釈の権限の所在を決定する権限」
物事の「意味」は人それぞれに異なる。しかし、人それぞれに物事を全く異なる形で捉えていては、人間関係が上手く機能しなくなったり、弱い立場の人の「解釈」が強い者によって無視されたりする。そのため、この状況において、ある物事の「意味」を誰が決めるのか(=解釈の権限の所在)を決定しておく必要がある。この働きをするものを「解釈の権限の所在を決定する権限」と呼ぶ。
例:「セクハラ」
女性社員である私が、上司から腰を触られたとする。この出来事について、改正男女雇用機会均等法の成立前と後で比べてみる。
(昔)私は「腰を触られて不快だ」と感じたが、力の強い上司が「これはセクハラじゃない」と言われた。初めは反論したが、上司が意見を変えなかったため「仕方ないか」と自分を納得させ、「これはセクハラとはみなされないのだな」とあきらめた。
(今)”被害者”である私が「セクハラをされました」と言えば、上司の腰を触る行為は、社会的にも法的にも「セクハラ」であると認められうる。上司は、私に「セクハラ」と言われやしないかとビクビクしている。
その行為が「セクハラ」であるかどうかによって、その後の上司の処遇が数ある選択肢から一つに決定されるわけだから、その行為がセクハラか否かもどちらかに決められなければならない。つまり、「ある立場からするとセクハラだが、別の立場からするとセクハラではない」というように、「解釈」に多様性を認めるわけにはいかない。よって、この「解釈」がどうやって最終的に一つに定まるか、それを考察することが必要である。
昔は、「その場においてその行為がセクハラであるかどうかを決めるのが誰か」ということは、あらかじめ決まってはいなかった。つまり、お互いがそれぞれにその場の物事は自分が解釈していい(自分に解釈の権限がある)と思っていた。そして、それぞれの意見をぶつけ合った結果として、力の強い立場にいた上司の「解釈」が通った。
しかし、現在では法によって、「その行為がセクハラであるかどうかを決めるのは被害者である」と決められており、そのことについて、その場の他のプレイヤーが意義を差しはさむことはできない。つまり、解釈の権限が「上司」ではなく「被害者」側にあることを、互いの力を争う「前」から、あらかじめ決まっている。
「セクハラ」の例ように、その集団内において、複数の「解釈」が対立するとき、どの解釈が採用されるかが「誰か」によって決定されなければ、その集団内の人間は、自分の行動を決めることができなくなる。
そのため、複数の解釈の対立に悩まされるコミュニティでは、それを解消するような「仕組み」が必ず要求されることになる。それが「解釈の権限の所在を決定する権限」である。
現代社会は「解釈の権限の所在を決定する権限」を必要とする
ポストモダンの特徴は、「大きな物語」が崩壊し、それぞれの個人の意思を超越するような「価値」の存在の確信が失われたところにある。「善」「正義」「美」といったものですら、あくまでそれは「見る人」が定めるものであり、見る人の立場に依存する相対的なものと認識されるようになった。
現代社会において、個人の自由と平等、そして多様性の尊重が強調されてきた結果、それぞれの人がそれぞれの物の見方を持っており、それを尊重しなければならないこと。つまり、それぞれの「解釈の権限」が強調されることになったのである。
繰り返すが、ポストモダンにおいては、それぞれの個人に依存せずに存在するような価値(=大きな物語)が崩壊した。そして、いかなる価値も、それぞれの個人の「解釈」に依存するものだとみなされるようになった。
「解釈」なくして「価値」は存在しない。これがポストモダンに生きる人間に課せられた、厄介な課題である。
解釈の多様性を認めれば、もちろん複数の解釈の対立が生まれやすくなる。そして、複数の解釈の対立が起きた時、どの解釈が採用するかを「誰か」に決めてもらわなければ、それぞれの個人は何を目指して行動すればいいのか分からない。「価値」が解釈に依存する以上、解釈が定まらないということは、目指すべき「価値」も定まらないということだからだ。
こういった理由から、人は無用な解釈の対立の増加を避けようとして、「解釈の権限の所在を決定する権限」を作ることになる。あらかじめ、この状況では誰の解釈が優先するのかを定めておくことで、解釈の対立を予防するのである。
「解釈の権限の所在を決定する権限」は、法律として示されることもあるが、多くは必要となったその場その瞬間において、「空気」という形で作られる。「解釈の権限の所在を決定する権限」の存在に慣れてしまった現代人は、(「空気」などの)集団の合意によって支持されなければ、自分の「解釈」を信じ通すことすら苦手になりつつある。
「解釈の権限の所在を決定する権限」が作り出す人間関係のルール
いかなる「解釈の権限の所在を決定する権限」も、基本的には解釈の権限の対立を平和的に調停することを目指して、集団の合意によって形成されるものなのだから、共通する大まかな特徴を持つことになる。
以下の3項目は、なかでもよく見られるルールを取り出したものである。
1.他者不可侵の原則:
誰もその人の代わりにはなれないのだから、人はそれぞれ「自分に関すること」、特に自分の内的体験は、その人にしか分からない。そのため、人は自分のことを他人に勝手に決めつけられない権利を持っている。つまり、自分に関することについては、その人に解釈の権限がある。
2.被害者優遇の原則(1番の派生):
ある人が何らかの苦痛を被った場合、その苦痛は本人にしか経験できないものであるため、その人が何に苦痛を感じるかとその苦痛の程度については、被害者自身の「解釈」が最も優先される。
3.弱者優遇の原則:
恵まれない者の意見は、恵まれている者よりも優先される。
私たちは、上のようなルールを漠然と意識しながら、「解釈の権限の所在を決定する権限」を形成する。
上のようなルールがあるおかげで、どのような利益があるだろうか? 上のルールは、マイノリティに優しいルールであると言える。
例えば、TVに出てくるゲイの人を目の前にして、「男が男を好きになるなんておかしい」と堂々と発言する人は少なくなっているだろう。むしろ、「おかしい」と感じてしまうこと自体すら「いけないことである」と考える人が増えているのではなかろうか。「あなたは異性を好きになるハズ」と私が勝手に決めることは、1番のルールに違反する。相手の領域について、こちらが勝手に「解釈」をすること自体が「いけないこと」になっている。
上のようなルールの出現により、私たちは常にかなり厳しい縛りの中で生きることを余儀なくされている。自分が「決めつけていい」エリアが極端に少なくなりつつある。
それが端的に表れているのが、「やさしい関係」である。精神科医の大平健は、著書『やさしさの精神病理』の中で、相反する二つの「やさしさ」の存在を指摘し、やさしさの意味が世代によって異なっていることを指摘した。
彼によると、古い意味での「やさしさ」は、相手の気持ちを「察する」ことだった。相手の気持ちを推し測り、それに対応することであった。身近に泣いている人がいたら、話を聞いてやり、慰めてあげるのが「やさしさ」であった。
だが、このような「やさしさ」は、相手の気持ちを「決めつけている」ために、ルール1番に違反する。そのため、このような「やさしさ」はむしろ非難の対象になり得る。
新しい意味での“やさしさ”は、相手の気持ちに「立ち入らない」ことである。相手の気持ちを勝手に推測するのはやってはいけないことであり、相手の気持ちが分からない時はむやみに関わらないのが“やさしさ”である。身近に泣いている人がいたら、そっと見守っておくのが“やさしさ”となる。
前者の「やさしさ」は治療的であり、後者の“やさしさ”は予防的である。「やさしさ」は、現在すでに傷ついている人を慰めることはするが、その代わり、意図せずして人を傷つけてしまうことがある。“やさしさ”は、不確実性の高い人の関わりを避けるため、人を間違って傷つける危険性は少ないが、その代わり、現在相手がすでに何らかの形で傷ついていたとしても、そのことには気づくことすらできない。
私たちの世代は、後者の“やさしさ”に支配された関係、すなわち「優しい関係」が蔓延している、という。「優しい関係」とは、「相手の気持ちに立ち入らないこと」「万が一にも、相手を傷つけないこと」が見えないルールとなって、互いを縛っているような関係である。
この人間関係の変化を象徴する出来事が「ナンパ」であろう。昔はかわいい子を見れば「かわいいね」と声をかけるのが礼儀だった、と言う。しかし、今では、そんな声をかける人間は変質者か何かだ、という感覚を持つ人が多いのではなかろうか。
1番の他者不可侵の原則により、他人の領域を勝手に解釈することは「いけない」行為と認識されるようになったのだ。その人が例え「かわいい」としても、それを他人が勝手に決めつけたり、評価したりすることは「いけないこと」として思われている。
このような人間関係の変化は、「解釈の権限の所在を決定する権限」の出現によって作り出された関係なのだ。
「越権」
「越権」とは、「解釈の権限の所在を決定する権限」によって、その物事についての「解釈の権限」は自分には存在しないと決定されている事柄について、何らかの解釈をしてしまうこと。つまり、「解釈の権限の所在を決定する権限」によって認められている「正当な解釈」と対立する「別の解釈」を生み出してしまうことを指す。
「越権」は、「解釈の権限の所在を決定する権限」への明確な違反である。現代において、「解釈の権限の所在を決定する権限」は、大きな物語のようなものではなく、その場の集団の合意によって形づくられているから、その合意を脅かそうとするものは、まさに「集団の合意」によって叩かれる。
セクハラの例を思い出していただきたい。「解釈の権限の所在を決定する権限」が成立する以前は、解釈同士の対立は、単純にお互いの解釈をぶつけ合い、力の強い方が通る、というものだった。いってみれば、この段階では個人対個人の「ケンカ」と見なされており、他の人間は出てこない。負けたほうは単純に「力が弱かった」だけであり、それが悪いとか間違っているとかの話にはならない。
だが、「解釈の権限の所在を決定する権限」が成立した後においては、解釈同士の対立は「正当性」や「善悪」の問題になる。建前上、この対立は平和的に解決されていなければならないので、その解釈が棄却された理由が「力の弱かったから」では通らない。「解釈の権限の所在を決定する権限」が選んだ「解釈」が「正当」であり、対立する他の解釈は「不当」なものとして徹敵的に叩かれることになる。他の解釈を叩くことを正当化するために、その解釈は「間違ってる」とか、「悪」だとか、「権利の侵害」だとか、そういった言葉が並ぶことになる。これはもはや力のぶつけ合いとしての「ケンカ」ではなく、「集団の合意」による「違反者」の粛清である。
もし、酷く傷ついているセクハラの被害者に対して、それを見た全く関係ない第三者が「触られたって大したことないじゃん、騒ぎ過ぎなんじゃないの」と言ったらどうなるか。被害の大きさを決定する権限は被害者にしかないのだから、彼にはこの問題に口を出す権利が無い。おそらく、彼は袋叩きに遭うだろう。彼を非難する者は、単純に彼が憎いだけでなく、彼を非難する行為は集団によって正当化されている、と思っている。
Twitterなどの「炎上」は、「越権」の分かりやすい例である。その問題について「正当な解釈」と見なされているものとは異なる解釈を、「解釈の権限の所在を決定する権限」によって解釈の権限からはじき出されている人間が口に出した時、彼の意見は、集団の合意によって徹底的に粛清される。
また、いじめ問題もこの構造に似ている。土井隆義「友だち地獄」の一部をいかに引用した。
現在の若者たちは、日本青少年研究所の所長である千石保が「マサツ回避の世代」とも呼ぶように、「優しい関係」の維持を最優先にして、きわめて注意ぶかく気を遣いあいながら、なるべく衝突を避けようと慎重に人間関係を営んでいる(『マサツ回避の時代』PHP研究所、一九九四年)。しかし、このような互いの相違点の確認を避ける人間関係は、その場の雰囲気だけが頼りの揺るぎやすい関係でもある。だからそこには、薄氷を踏むような繊細さで相手の反応を察知しながら、自分の出方を決めていかなければならない緊張感がたえず漂っている。
このような人間関係の息苦しさは、ある中学生が創作した「教室は たとえて言えば 地雷原」という川柳にも巧みに表現されている。しかし彼らは、その人間関係から撤退する選択枝をもちあわせていない。なぜなら、たとえ息苦しいものだとしても、その人間関係だけが、彼らの自己肯定感を支える唯一の基盤となっているからである。
かくして彼らは、教室のいたるところに埋没された地雷を踏むことのないように細心の注意を払いながら、互いの配慮の視線をさらに繊細なものに高めていく。互いの反感が露呈してしまわないように、対立の要素を徹底的に排除しようとし、さらに高度な気遣いをともなった人間関係を営んでいく。ここには、人間関係の過剰な期待と、それがもたらす過剰な息苦しさをめぐって、相互に補強しあうような関係が成立している。
評論家の山本七平がかつて説いたように、私たち日本人にとって、「「空気」とはまことに大きな絶対権をもった妖怪」でありつづけてきたが(『「空気」の研究』文藝春秋、一九七七年)、とりわけ今日の若者たちの間では、「優しい関係」を媒介にその絶対権がさらに高まり、急速に先鋭化しつつある。「優しい関係」が営まれる場の空気の決定権を握っているのは、そこに参加している一人ひとりの個人ではない。ましてや、その場を取り仕切るリーダーなど最初から存在していない。そうではなくて、「優しい関係」そのものが、空気の流れを決定する圧倒的な力を持っているのである。
土井隆義「友だち地獄 「空気を読む」世代のサバイバル」はじめに より一部引用
「空気」と呼ばれる存在は「解釈の権限の所在を決定する権限」とほとんど同じ機能を持っており、その場の解釈を一つに定めている。もし、その「空気」を乱すような行為をすれば、それはすぐに「越権」と取られ、極端な粛清が起こることになる。
「越権」への恐怖、「不確実性への耐性」
現代社会に生きる若者は、「越権」への恐怖を幼い頃から刷り込まれて育ってきたわけだから、「解釈の権限」を行使することに極めて臆病であり、過敏である。越権とは、「解釈の権限の所在を決定する権限」によって自分に「解釈の権限」が与えられていないにもかかわらず、その物事について「解釈の権限」を行使してしまうことであるから、「解釈の権限」の行使は、「越権」のリスクを冒すことに他ならない。
「越権」への恐怖に脅えるあまり、若者は以下のような圧力の中に生きている。まず、常に「解釈の権限の所在を決定する権限」が誰に解釈の権限を与えているのかにアンテナを張り続け、その解釈の権限が生み出した解釈に従わなければならない。そして、「解釈の権限の所在を決定する権限」が自分に「解釈の権限」が与えている状況でなければ、自分の好きなように物事や状況を感じ、解釈することすらできない。「感じるままに動く」ことや、「自分の物の見方を信じること」がこんなに困難な時代もないのではないか。
この恐怖、自分の好きなように物事を感じ解釈することへの恐怖と圧力こそが、現代社会特有の「息苦しさ」の正体だと言えるのではないだろうか。常に「解釈の権限の所在を決定する権限」が存在する環境下では、自分が何らかの判断や解釈を行う時、かならずその判断や解釈に「正当性」を要求される。自分が何らかの「価値」を信じようとしても、それに「客観的な根拠」が無ければ、それを信じることすら難しい。私たちは常に、「解釈の権限の所在を決定する権限」から自分に権限が与えられた範囲でしか、物事を自由に解釈することができない。
このような圧力の中で生きていると、『「解釈の権限の所在を決定する権限」によって「解釈の権限」が与えられている「解釈」』に従っていないと、常に不安になりやすくなる。例えば、若者は、指示されたことはできても、指示されずともとりあえず自分なりに動いてみるということができない、なんてことがしばしば言われる。何事にも正解を求める世代、マニュアルを欲しがる世代だ、といった意見がテレビなどで聞かれることがある。
これは「解釈の権限の所在を決定する権限」によって自分に「解釈の権限」が与えられているかが不明確な中で「解釈の権限」を行使することへの不安が原因である。マニュアルや上司の指示などの誰が見てもそれが「全体の合意」として正しいものに認められていないと、自分の行動を組み立てることができないのである。
このような若者の特徴は、「不確実性への耐性」が弱いという表現で指摘されている。自分がもしかしたら「正しくない解釈」に従ってしまっているのではないか、という不安が強く、常に「状況が確実に定まっている」ことを求めてしまう。
例えば、私の話をすると、初めてのお店(例えばラーメン屋とか)に入るときでも、どうふるまえばいいのか分からず不安になってしまう。注文はどのタイミングで声をかければいいのか、どこに座ればいいのか、お会計はいつなのか、荷物はどこに置くのか。初めてのお店に入ると、「分からないこと」が怒涛のように襲ってくる。それを考えると怖くなってしまい、結局お店に入るのが嫌になって帰ってしまうのである。
「越権」への恐怖は、現代のコミュニケーションを支配するとても大きな原動力である。ネット上のコミュニケーションを見ると、それがとてもよく表れている。特に他人からの監視の目が強くなるネット上においては、何らかの発言(=解釈)を外に向けて発信する度、他人との「解釈の対立」を生み出さないために細心の注意を払うことになる。ネタとして言ったり、メタ化したり、他のキャラにしゃべらせたり、できるだけ「私個人」の意見であることを強調したり、自虐したり、体言止めにしたり、とにかくありとあらゆる工夫を凝らすことになる。
だが、この特徴は必ずしも悪いものではない。これは他人を慮り、社会的合意を遵守しようとするメンタリティとコインの裏表である。自分に解釈の権限が無い状況下でも臆せずに解釈の権限を行使できる姿勢は、知りもしない出来事についてテキトーなことを言いながらぐいぐいと踏み込んでくる、いってみれば「オバチャン」的な押しつけがましさや厚顔無恥さと同じものである。酷く傷ついているセクハラの被害者を見た全く関係ない第三者が、深く考えずに「触られたって大したことないじゃん、騒ぎ過ぎなんじゃないの」と言って被害者のバンバンと肩をたたくような姿勢と同じものなのだ。
だが一方で、このような思い切りは生きていく上で必要不可欠でもある。ありとあらゆる出来事に対して、常に「正解」を求めることはできない。何も知らない状況、出来事に対しても、自分勝手な解釈を押し通すことが必要になるときもある。人を相手にする仕事をすればするほど、そのような「思い切り」の必要性は高まる。仕事をしていれば、どうやって自分の都合を相手に押し付ける必要性が出てくる。自分は押し付けたくないのに、生きていくためには自分の都合を押し付けなければならない。それは大きな「生きづらさ」として経験される。
だが、「越権」への恐怖が強まると同時に、まったく逆の側面も強まるようになった。
「解釈の権限の所在を決定する権限」によって自分が「解釈の権限」を与えられていると確信できる状況ならば、「解釈の権限」を行使することに躊躇いがなくなってきたのである。
これは先の「粛清」にも表れている。自分の解釈が「解釈の権限の所在を決定する権限」に認めてもらっていると感じられる時、人はいとも簡単に残酷になる。
昔は、「解釈の権限」の行使は、善も悪も無いただの「力」の行使であった。だからこそ、自分の「力」が誰かを傷つけてはいないか、自分が責任を持たなければいけない、という意識と圧力が強かった。しかし、今では「解釈の権限」は、「正当性」の問題にすり替わっている。よって、「解釈の権限」を持っているということは、すでに自分は「正当」なのだ、という意識に変わっている。そのため、解釈の行使に伴う責任感や危険意識がなくなってしまったのだ。
また別の側面として、解釈の対立を解消するためならば、人間関係をいとも簡単に切り捨てるようになった、とも言われる。SNSでは、「ブロック」という手段で簡単に人とのつながりを断てる。解釈の対立を生むくらいなら、相手との関わりを断ってしまおう、という思考回路がさほど珍しいものとは言えなくなっている(私もそうだ)。
いかに自分に居心地のよい空間を作り出すか?
「解釈の権限の所在を決定する権限」の登場により、いくつもの圧力や制限が生み出されるようになった。常に「正当な解釈」の存在を意識し、それに合わせなければいけなくなってしまった。
このような環境下において、人はどのような空間を求めるだろうか? ここでは、今まで上げた「解釈の権限の所在を決定する権限」の存在によって生まれる生きづらさを解消するための具体例をいくつか紹介する。
・分かりやすくてみんなが共有できる「解釈の権限の所在を決定する権限」を生み出す
法律もマニュアルもこの方法に分類されるだろう。「これが全員の合意ですよ、この範囲なら正しい行いですよ」という行動指針(解釈)と、それを規定するもの(解釈の権限の所在を決定する権限)を、全体の合意によって定めてしまう。「正当な解釈」が自分にも分かるようにキレイでシンプルに示されていれば、それほど悩むことなく行動することができ、居心地の良さにつながる。
例えば、当事者研究会では、初めにレジュメをみんなで読む時間を取るが、このレジュメを全員で読む時間が「解釈の権限の所在を決定する権限」であり、このレジュメの中に書かれたルールが「正当な解釈」ということになる。このように初めに全員で「ルール」を確認し合う方法はなかなか有効である。もちろん、「ルール」に賛同できない人がいる場合ももちろんあるので、この会は強制的なものではなく、参加したくなければ参加しなくても何の不利益もない、というルールが確保されていることが重要である。
また、宗教的な方法もこの方法に分類される。その集団内において最も権限の強い何者かを定め、それが定める「教義」に従っている間は、不安を感じずに済む。最近オタクコミュニティの風習は宗教に近いのではないか、という視点で分析する考えがあるが、いわゆるオタク文化での定型話法(AA、淫夢など)は、このような「教義」の役割を果たしている可能性がある。
・「解釈の権限の所在を決定する権限」が存在しない空間を作る
どれが正当な解釈かを一つに定める必要がなければ、「解釈の権限の所在を決定する権限」は必要ない。答えを一つに決めることなく、それぞれが自分の意見を好き勝手にだらだらとしゃべる形式であれば、「解釈の権限の所在を決定する権限」は不必要になり、どの解釈も「それはそれでよし」ということになる。「越権」の心配がなくなるし、自分の「解釈」の正当性が常に評価されているような息苦しさが減り、居心地の良さにつながる。
自助会においてしばしば採用される会話方法に、「言いっぱなし、聞きっぱなし」という方法がある。これは、参加者は自分の番になるたびに自分のことをしゃべり、周りの人は質問も返答もせずただ聞いている、という方法である。この形では、それぞれの参加者が勝手に自分の意見(解釈)を語るだけで、それぞれの解釈の間に関わりが生まれないので、「解釈の権限の所在を決定する権限」は必要ない。
このような空間づくりには、「共感や協調を押し付けない、参加者みんなの意見を無理に一つに合わせようとしない」という空気の存在が重要になる。Twitterは、「つぶやく」というシステムの特徴上、比較的この空気が強く、「解釈の権限の所在を決定する権限」が生まれにくい。
・「解釈の権限」を取り戻す
自分に「解釈の権限」があれば、自分の感じるままに動くことができるので、自分の自信にもつながるし、居心地の良さにつながる。
当事者研究では、「自分の生きづらさは自分が一番の専門家」という言葉を採用している。自分の生きづらさについては、自分に「解釈の権限」がある、という考え方は、かなり多くの人に納得してもらえるので、自分の生きづらさについて語ることで、「解釈の権限」が自分にある感覚を取り戻すことができる。
ちなみに、科学(医学、心理学、社会学)は、あらゆるものに対して強い「解釈の権限」を持っているため、科学者や専門職(医師や臨床心理士)によって解釈されたりコントロールされたりする経験を長年続けていると、自分で自分を解釈できる権限が奪われていく特徴がある。逆に、科学を手にする者は、自分があらゆるものを解釈できるような全能感に浸れるが、科学によって「解釈すること」そのものに、生きている人を「解釈される対象物」に貶める効果があることは注意すべき点である。
「知識」を持つことで、「解釈の権限」は強まる。また、当事者としての自分から距離を置き、「観察者」として自分を客観視・メタ視することによって、「解釈の権限」は強まる。この方法は良い面だけでなく悪い面もかなりあるが、使える方法である。
まなざしの不足と自己語りの時代
1番の「他者不可侵の原則」によって、私たちは自分のことは他人に口出しされない自由を手にすることになったが、一方でこのルールは、他者のとのつながりの希薄さを生み出すことにもなる。
まず、昔と違い、相手に自分の気持ちを「察して」もらうことは期待できなくなった。街中を歩いていたら突然ナンパされることがなくなったように、自分が意思表示をしなければ、「向こうから自分へ勝手に関わってきてくれる」可能性は一気に減った。近所付き合いのように、強制的に参加を押し付けられるような人間関係は少なくなった。
相手に自分を「分かって」もらいたければ、自分で自分のことを語り、聞いてもらわなければならない。なぜなら、「私に関すること」について、解釈の権限を持っているのは私だけだからである。自分が誰かと関わりたければ、自分で意思表示をするしかなく、それは全て「自分の意志で」決めたこととして扱われる。昔とは違い、人間関係の「選択」の責任は、すべて私に帰属する。
この世代が抱えるもう一つの大きな問題は、「まなざしの不足」である。自分のことを見て、自分のことを評価し、自分のことを解釈してくれるような「まなざし」が不足しているのである。「君はこうするべき」とか「君は明日こうしたら良いよ」とか「君のこういうところがいいよね」とか、そういう「解釈」を押し付けてくる働きが少なくなってしまったのだ。
自分が意図的に「外に向けて発信する解釈」を監視する目線は強まるばかりなのに、自分が「内に秘めているモノ」に向けて視線を向けてくれる人はどんどん減っている。私が他者に向ける一つ一つの行動や発言は常に評価されているにも関わらず、私の「気持ち」や「目指すべき未来」や「生きづらさ」とでも呼ぶべきものに目を向けてくれる機会は、何もしなければどんどん減っているのではないか。
SNSなどの「自己語り」式のコミュニケーションが増えている現象の裏には、このような事情があるのだと感じる。昔のように、相手に自分の気持ちを「察して」もらうことはできないのだから、相手に自分を「分かって」もらいたければ、自分で自分のことを語るしかない。たとえ「外」に自分の想いを出すことにリスクが伴うとしても、自分の「内」にまで踏み込んできてくれる人はいないのだから、自分から発信するしかないのだ。何より、「自分のこと」に関しては「解釈の権限」は自分にあるのだから躊躇う必要はない。
意地悪なことを言えば、自分の「解釈の権限」を高めるためには自虐的な語りの方が効果が高い。2番や3番のルールがあるからだ。そのために、「生きづらさ」についての語りが増えているのではないか、とも思う。だが、これは単純に、楽しいことよりもつらいことの方が「分かってほしさ」が高いからだ、という面もあるだろう。この点については断定を避ける。
おわりに
立場の強い者、力のある者が「解釈の権限」を行使することの暴力性に気づいた人たちは、「解釈の権限の所在を決定する権限」を作って、その暴力性を制御しようとした。それはセクハラ対策など、マイノリティが虐げられている状況を改善することにはつながったが、一方で新たな「生きづらさ」を生み出している。
何が良いのか、何を目指すべきかということではなく、何が起きているかを記述するための言葉を知ることが大事だと思う。たどり着きたい目的地を定めずに、このコミュニケーション形式が悪いとか問題点を指摘し合うのは、それ自体に危険性が伴う。
ただ、個人的な感慨としては「解釈の権限の所在を決定する権限」の存在に慣れている人は、他人の領域を冒すことに対してあまりにも過敏すぎるのではないか、と思う。もちろん他人の領域に踏み込むことは私も最大限に慎重であるべきだと思っているし、よくお前は慎重すぎると周りの人から言われる。だが、それが必要であり有効であると思われるなら、きちんと自分の行為に責任を持ち、覚悟を決めて、「越権」を冒す勇気も必要なのではないだろうか。アニメ「プリズマ☆イリヤ」でも言っていた。友達が困っているなら、その事情に踏み込むことも必要だと。
そのような自分の行為に、集団の合意によってあらかじめ与えられるような「正当性」があると思ってはいけない。自分にはその行為を行う正当な権利が与えられていると思ってはいけない。だが、その行為はおそらく「必要」なのだ。批判はされるだろうが、解釈の対立そのものが悪いわけではない。お互いの解釈をぶつけていけばいいのである。むしろ、もっと解釈を争っていくべきなのではないだろうか。
以前、「人生の文脈を交わす会」という会に参加したとき、「理不尽」を経験しておくことの必要性について語ったことがあった。理不尽とは、自分とは異なった「理不尽な」解釈を無視やり押し付けられることである。「否定しても良い」解釈と出会い、それと1対1で力をぶつけ合い、叩き潰そうとする経験を積んでおかなければ、「解釈の対立」への耐性は身に付かないのではないだろうか。「解釈の対立」に、自分の力で勝つ経験を積むことで、自分の解釈を押し通す勇気が身に付くのではないだろうか。最終的にその会では、「コンビニで100円で理不尽体験を売ろうぜ」なんて話をしていた。僕は元気な時に買ってみたい。そうじゃないと負けそうだし。